はじめに
 近年、平和・紛争分析の分野において「紛争の予測」は注目を集め、機械学習などの新しいコンピュータ技術を用いた研究も多く発表されている(Hegre et al. 2017)。その背景には、かつての平和・紛争分析において重視された「過去の紛争を説明する」ことに特化した紛争モデルよりも、「未来の紛争を予測する」ことに長けたモデルの方が、平和政策の決定者にとって好まれるようになったという事情がある。世界の武力紛争件数はソ連解体の1991年にピークを迎え、その後しばらくは減少傾向にあった。しかし2015年には52件の武力紛争が存在し、件数の上では再びピークに並んだ。また、冷戦後の武力紛争はそのほとんどが国内紛争として戦われてきたという性質を持つ(Dupuy et al. 2017)。なおUppsala Conflict Data Program(UCDP)では、武力紛争は『少なくとも一方が政府である2つの武装勢力間で生じる、統治および/もしくは領域に関しての不一致のための争いであり、年間25人以上の戦闘関連死者が出たもの』と定義され、その中でも『政府と非政府勢力によって争われ、他国の介入を受けないもの』は国内紛争と定義される(Uppsala University : online, 翻訳は筆者)。本論文でもこの定義に従う。また、単に「紛争」という場合も「武力紛争」と同義のものとして扱う。これらの紛争がもたらす、生命・人権・経済・環境への甚大な被害を回避するため、正確な予測を行うことは重要度の高い研究テーマである。
近年、平和・紛争分析の分野において「紛争の予測」は注目を集め、機械学習などの新しいコンピュータ技術を用いた研究も多く発表されている(Hegre et al. 2017)。その背景には、かつての平和・紛争分析において重視された「過去の紛争を説明する」ことに特化した紛争モデルよりも、「未来の紛争を予測する」ことに長けたモデルの方が、平和政策の決定者にとって好まれるようになったという事情がある。世界の武力紛争件数はソ連解体の1991年にピークを迎え、その後しばらくは減少傾向にあった。しかし2015年には52件の武力紛争が存在し、件数の上では再びピークに並んだ。また、冷戦後の武力紛争はそのほとんどが国内紛争として戦われてきたという性質を持つ(Dupuy et al. 2017)。なおUppsala Conflict Data Program(UCDP)では、武力紛争は『少なくとも一方が政府である2つの武装勢力間で生じる、統治および/もしくは領域に関しての不一致のための争いであり、年間25人以上の戦闘関連死者が出たもの』と定義され、その中でも『政府と非政府勢力によって争われ、他国の介入を受けないもの』は国内紛争と定義される(Uppsala University : online, 翻訳は筆者)。本論文でもこの定義に従う。また、単に「紛争」という場合も「武力紛争」と同義のものとして扱う。これらの紛争がもたらす、生命・人権・経済・環境への甚大な被害を回避するため、正確な予測を行うことは重要度の高い研究テーマである。
冷戦後の紛争研究の流れ
 従来、前述の性質をもつ冷戦後の紛争は、冷戦終結による世界秩序の変化や、民族的・宗教的対立から生じたと説明されてきた。これに対する計量的な分析としてまず試みられたのは、変数の統計的有意差を示す手法である。この手法により、Fearonらは従来の理論が国内紛争の発生を十分に説明することはできず、むしろ貧困(国民1人あたりの所得により評価)、政治変動、山地の多い国土、人口過多などの反乱勢力にとって有利な条件の方が国内紛争の発生には重要であることを示した(Fearon & Laitin 2003)。さらにCollierらも、民族的・宗教的差異や不平等といった「不満」を表す変数よりも、国内総生産(GDP)の上昇率などの経済的変数の方が国内紛争の発生に対する説明能力が高いことを示し(Collier & Hoeffler 2004)、既存の紛争理論に異議を唱えた。これらの研究は、過去に発生した紛争をより良く説明できる要因を探すことを目標としていたため、本論文ではこれを「説明研究」と呼称する。しかし、説明研究の成果に基づいて設計されたモデルは、紛争の発生を事後的にも予測できないことが後に明らかになった。具体的には、Fearonらのモデルは15件の紛争を検出するために66件の偽陽性、Collierらのモデルは34件の紛争を検出するために110件の偽陽性を生じたのである(Ward et al. 2010)。
従来、前述の性質をもつ冷戦後の紛争は、冷戦終結による世界秩序の変化や、民族的・宗教的対立から生じたと説明されてきた。これに対する計量的な分析としてまず試みられたのは、変数の統計的有意差を示す手法である。この手法により、Fearonらは従来の理論が国内紛争の発生を十分に説明することはできず、むしろ貧困(国民1人あたりの所得により評価)、政治変動、山地の多い国土、人口過多などの反乱勢力にとって有利な条件の方が国内紛争の発生には重要であることを示した(Fearon & Laitin 2003)。さらにCollierらも、民族的・宗教的差異や不平等といった「不満」を表す変数よりも、国内総生産(GDP)の上昇率などの経済的変数の方が国内紛争の発生に対する説明能力が高いことを示し(Collier & Hoeffler 2004)、既存の紛争理論に異議を唱えた。これらの研究は、過去に発生した紛争をより良く説明できる要因を探すことを目標としていたため、本論文ではこれを「説明研究」と呼称する。しかし、説明研究の成果に基づいて設計されたモデルは、紛争の発生を事後的にも予測できないことが後に明らかになった。具体的には、Fearonらのモデルは15件の紛争を検出するために66件の偽陽性、Collierらのモデルは34件の紛争を検出するために110件の偽陽性を生じたのである(Ward et al. 2010)。
こうしたモデルと現実の乖離を克服するために近年行われている「予測研究」は、過去の紛争データに基づき、未来の紛争も予測できるような汎用モデルを構築することを目標とする。このことは、利用可能なデータを、モデル構築用データと性能評価用のデータに分割することにより実践され、この作業により、モデルが特定の紛争データにのみ過剰適合すること(過学習)を避けることができる。その結果モデルの予測精度は向上し、Muchlinskiらがランダムフォレストという機械学習アルゴリズムを用いて構築したモデルは、性能評価用データに対する予測においてReceiver Operating Characteristic(ROC)曲線のArea Under the Curve(AUC)が0.91という結果を示した(Muchlinski et al. 2016)。しかし、Chadefauxは予測研究には根本的な限界があることを指摘した(Chadefaux 2017)。彼が掲げた問題点は以下の2点にまとめることができる。第一に、紛争や政治のメカニズムは予測ができないほど複雑である。ポパーによれば、多くの事物、自然過程および自然現象は「雲」(『きわめて不規則で無秩序的な、多かれ少なかれ予測不能な物理的体系』)と「時計」(『規則的で秩序のある、きわめて予測可能な振舞いをする物理的体系』)を二つの極端としたその中間に位置付けることができる(ポパー 1974 : 235)が、Chadefauxは、紛争のメカニズムはより雲に近い性質を持つと主張する。さらにタレブは「Black Swan」という本質的に予測が不可能な事象が存在することを主張した(タレブ 2009 : 上巻3-4)。したがって、紛争のメカニズムが雲やBlack Swanとしての性質を持つ場合、その予測は限りなく困難になると考えられる。第二に、人間は意図的に予測を無効にすることができる。例えば、「今年は国内紛争が起こらない」との予測が発表された直後に、反政府勢力が奇襲攻撃を加えるケースが考えられる。これは単純であるが、確実に予測を無効化することができ、したがって予測は根本的に不可能であるとする議論が成立する。

説明研究と予測研究の比較
以上を総括すると、平和・紛争分析における予測研究には、次のような特徴があることがわかる。第一に、予測研究は説明研究よりも高い実用性を有している。説明研究のモデルに比べ、予測研究のモデルは現実の紛争に適応しやすいため、政策決定者に好まれる傾向にある。第二に、予測研究は説明研究に比べ、モデル間の性能比較が容易である。説明研究において統計的有意差を示された変数の有効性を後に否定することは困難であり、結局どのモデルが優れているのかは曖昧である。一方、予測研究においては、ROC曲線やThe Separation Plot(Greenhill 2011)などの手法を用いて、モデルの性能を予測精度として容易に比較することができる。よって、新しい研究がどれほど性能の向上に貢献したかを明確に示すことが可能である。以上2つの利点は、平和・紛争分析の研究が実際の平和構築に貢献する上で重要な性質であり、従来の説明研究においては達成できなかったものである。しかし第三の特徴として、予測研究にはその根本的な限界があることが指摘されている。これらは明らかに予測の精度や意義を損なうものであるが、現在のところ有効な対策は存在しない。

論文の構成
そこで本論文では、これらの限界を克服するため、予測研究の焦点を従来の「紛争勃発の予測」から、「前紛争状態の予測」へと移すことを提唱する。ここで「前紛争状態」を「まだ紛争は勃発していないが、その兆候が認められる状態」と定義する。この「前紛争状態」という概念は、生体・生態系・経済などを「複雑システム」として捉える「システム変動分析」の手法に基づく考え方であり、以下、このシステム変動分析についても適宜説明を加えながらその妥当性を検証する。よって本論文では、まず複雑システム並びにシステム変動分析について説明し、その後に前紛争状態の具体的な予測方法を示す。その後、なぜシステム変動分析の考え方が紛争分析に適応できるのか、前紛争状態の予測へと研究の焦点を移すことで、なぜ複雑なメカニズムを持つ紛争の予測が可能となり、かつ、なぜ人為的な予測の無効化を受けてもその意義を保つことができるのかについて考察する。この時、国内社会を1つの複雑システムと見る観点から、分析の範囲は国家レベルとし、国内紛争に焦点を当てて議論を進める。すなわち、議論の対象となるのは「前国内紛争状態」である。最後に、本論文が提唱した手法が抱える問題点とその対策についても分析し、全体を総括する。
複雑システムとシステム変動分析
複雑システム・システム変動分析・臨界減速
 システム変動分析とは、複雑システムの挙動を分析するために考案された手法、並びにその研究分野のことを指す。複雑システムは一般に、「多数の要素から構成され、要素間相互作用によって、予期できないような高次の秩序や機能を生み出しうるシステム」と定義され、生体、生態系、経済などがその例である。複雑システムは通常とある安定状態を持ち、外圧の影響により微小な状態変化が生じた際には、修復力が働いて即座にもとの安定状態へと復帰する。しかし、時に複雑システムはもとの安定状態に戻るのではなく、異なる安定状態へと遷移することがある。このような変化が生じる臨界閾値は「転換点」と呼ばれ、その前後でシステムに大きな変動が見られることが確認されている(Scheffer et. al 2009)。具体例としては、生体における病気の発症、生態系における個体数の激減、経済における恐慌などが考えられる。これらの変動は唐突かつ急速に生じるため、システムの構成員やその外部に対して大きな脅威となりうる。よって、システム変動分析は、複雑システムが転換点に近づきつつあることを検知することが目標となる。現在、転換点付近では様々な予兆が現れることが知られているが、最も代表的な分析理論は臨界減速(Critical Slowing Down:CSD)と呼ばれる。この理論では、システムを一変数の時系列変化として計測した時、転換点付近では外圧による微小変化から安定状態への復帰に遅れが生じることに注目し、その変化を変数の標準偏差と自己相関係数の上昇によって捉える。このことは、感覚的には、システムが転換点に近づくにつれ、外圧に対する脆弱性が増していると考えることができる(転換点の存在、転換点付近での変数の標準偏差・自己相関係数の上昇についての数学的な説明は、Scheffer et. al 2009 : Box1~3参照)。
システム変動分析とは、複雑システムの挙動を分析するために考案された手法、並びにその研究分野のことを指す。複雑システムは一般に、「多数の要素から構成され、要素間相互作用によって、予期できないような高次の秩序や機能を生み出しうるシステム」と定義され、生体、生態系、経済などがその例である。複雑システムは通常とある安定状態を持ち、外圧の影響により微小な状態変化が生じた際には、修復力が働いて即座にもとの安定状態へと復帰する。しかし、時に複雑システムはもとの安定状態に戻るのではなく、異なる安定状態へと遷移することがある。このような変化が生じる臨界閾値は「転換点」と呼ばれ、その前後でシステムに大きな変動が見られることが確認されている(Scheffer et. al 2009)。具体例としては、生体における病気の発症、生態系における個体数の激減、経済における恐慌などが考えられる。これらの変動は唐突かつ急速に生じるため、システムの構成員やその外部に対して大きな脅威となりうる。よって、システム変動分析は、複雑システムが転換点に近づきつつあることを検知することが目標となる。現在、転換点付近では様々な予兆が現れることが知られているが、最も代表的な分析理論は臨界減速(Critical Slowing Down:CSD)と呼ばれる。この理論では、システムを一変数の時系列変化として計測した時、転換点付近では外圧による微小変化から安定状態への復帰に遅れが生じることに注目し、その変化を変数の標準偏差と自己相関係数の上昇によって捉える。このことは、感覚的には、システムが転換点に近づくにつれ、外圧に対する脆弱性が増していると考えることができる(転換点の存在、転換点付近での変数の標準偏差・自己相関係数の上昇についての数学的な説明は、Scheffer et. al 2009 : Box1~3参照)。
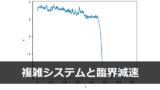
動的ネットワークマーカー(Dynamic Network Marker:DNM)理論
分析の射程を多変数に拡張した手法としては、生体における動的ネットワークバイオマーカー(Dynamic Network Biomarker:DNB)理論(Chen et al. 2012)、また、より一般のシステムに対しては動的ネットワークマーカー(Dynamic Network Marker:DNM)理論がある(Liu et al. 2015; 中川ら 2016)。この理論では、多くの変数がネットワーク構造をとるシステムにおいて、システムが現在の安定状態から別の安定状態へと転移するに際し、その直前に以下の3つの性質を満たすような特定の変数のグループが存在することに注目する。すなわち、(1)転移に近づくと、グループ内の変数の標準偏差が急激に上昇する、(2)転移に近づくと、グループ内の変数同士の相関係数の絶対値が急激に上昇する、(3)転移が近づくと、グループ内の変数とグループ外の変数の間の相関係数の絶対値が急激に減少する、である。この変数のグループのことを動的ネットワークマーカー(DNM)と呼び、I = SDd・PCCd / PCCoと定義されたDNMスコアIの上昇を評価することにより、システム変動の予兆、すなわち「前変動状態」を検出することができる。ここで、SDdはDNMに含まれるすべての変数の標準偏差の平均、PCCdはDNMに含まれる変数同士のすべてのペアの相関係数の絶対値の平均、PCCoはDNMに含まれる変数と含まれない変数同士のすべてのペアの相関係数の絶対値の平均である。後に、現実的なシステムに対する分析を行う際にはPCCoが期待されるものとは逆の挙動を示すことが明らかとなり、DNMスコアはI = SDd・PCCdと再定義された(中川ら 2016)。以上よりシステム変動分析においては、一変数・多変数によらず標準偏差と相関係数の重要性が高く、原理的には、それぞれ安定状態への復帰の遅れと変数間の相互作用の増強を反映していることがわかる。
データの収集と機械学習の導入
紛争分析は主に多変数を用いて行われる。分析の範囲を国内レベルに限定した場合、変数としてGDP上昇率や乳児死亡率、Human Right Protecting Score(Fariss 2014)など様々なデータが利用可能であり、これらは国内政治システムにおける経済、衛生、人権といった側面を反映する。国内紛争が生じるとこれらの変数は大きく変動するが、国内政治システムが複雑システムとしての性質を有するならば、それ以前にデータの標準偏差や相関係数の上昇が予兆として現れている可能性が高い。これにより検出される状態が「前国内紛争状態」である。しかしCSDやDNM理論においては、システム変動に際して標準偏差や相関係数、DNMスコアIが相対的に上昇することは示されているが、どの程度値が上昇したらシステムは転換点に近づいていると言えるのか、という基準が存在しないことに注意すべきである。そこで本論文では、システム変動分析と機械学習を組み合わせて、この前国内紛争状態とそうでない状態を区別する手法を示す。
前紛争状態の予測手法
具体的な分析の手順として、筆者が現在、妊婦の血圧と心拍数のデータから妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)の発症予測をするために用いている手法を紹介する。基本となる考え方は、個々のデータの値そのものをモデルに与えるのではなく、ある程度の期間(ウインドウ)を取り、その期間における各データの平均、標準偏差、二変数間の相関係数、または2つの変数の標準偏差の平均と相関係数の絶対値の積(二変数間のDNMスコアI)などを新規の入力変数として用いることである。ここで、2点ほど注意すべき点が存在する。第一に、各変数のデータは期間内に上昇・下降傾向を持つことがあるため、このトレンドを取り除いた上で標準偏差や相関係数を計算する必要がある。第二に、入力される変数がデータ数に比べて多すぎると予測精度は低下するため、使用する変数は制限されなければならない。筆者の経験では、データの平均値、標準偏差、二変数間の相関係数の絶対値のみを入力変数として用いると、最も結果が安定すると思われる。
こうして入力された変数から、その期間の状態が転換点にある確率を機械学習させる。この転換点が、妊娠高血圧症候群の前病状態や前国内紛争状態に相当するものである。この時、1回の学習で優れたモデルが得られるとは限らないため、Colaresiらが提唱した手順に基づいてモデルを改良する(Colaresi & Mahmood 2017)。この手順は「Box’s loop」(Blei 2014)を改良したものであり、構築→適用→批判→思考→再構築のプロセスを繰り返すことに特徴がある。手順の初めに、すべてのデータをモデル構築用データと性能評価用データに分割する点は予測研究に共通して行われていることであるが、この手順ではモデル構築用データを、さらに学習データと検証データに分割する。その上で学習データを用いて機械学習を行い、その精度を検証データにより評価する。ここで満足な結果が得られたと判断した場合は、性能評価用データを用いて精度を再評価し、この時の予測精度をモデルの最終的な性能として分析は終了する。しかし、検証データによる評価が満足できないものであった場合は、モデルに与える変数や用いるアルゴリズムを変更し、再度分割し直した学習データと検証データによりモデル構築と検証を行う。この手法の利点は、過学習を避けながら、繰り返し作業を通してより精度の高いモデルを構築できることである。また、モデルと検証データ間の矛盾点を定性的に分析してモデルの再構築を行うことで、予測対象への理解が深まると考えられる。
以上の手法を紛争予測に適用することで、予測研究の焦点は、「紛争勃発の予測(変動そのものの予測)」から「前紛争状態の予測(転換点への接近の予兆検出)」へと移行する。このモデルにより出力される確率値は、前紛争状態としての危険度、すなわち紛争の生じやすさとして考えることもできる。
システム変動分析の妥当性とその意義
では、なぜシステム変動分析の考え方が紛争分析にも妥当するのか。また、前紛争状態の予測へと研究の焦点を移すことで、なぜ複雑なメカニズムを持つ紛争の予測が可能となり、かつ、なぜ人為的な予測の無効化を受けてもその意義を保つことができるのか。以下、国内社会を1つの複雑システムと見る観点から、分析の範囲を国内レベルに限って考察する。
雲・Black Swanの分析に対する妥当性
システム変動分析の考え方が国内紛争分析について妥当するためには、国内政治システムが複雑システムとして捉えられなければならない。ここでポパーが提示した雲の性質は、予測が困難である点、無秩序のように感じられる規則に従う点において複雑システムの定義に合致する。特に、グローバリゼーションの影響下で、非政府団体(NGO)、多国籍企業、非合法組織、民間軍事会社などの非国家的主体の活動が拡大した現代の世界においては、国際関係のみならず国内政治システムも、多様なアクターの相互作用により構成されるシステムとしての複雑性を増していると言える。なお、ここで言うグローバリゼーションとは「科学技術の進歩とそれに基づく交通・通信・情報処理手段の高速化と低価格化に支えられて起こる、財・サービス・資本・人・情報の国境を超えた交流の高度化がもたらす、政治・経済・社会構造の再編成過程」と定義されるものである(遠藤 2006)。以上より、国内政治システムは複雑システムとしての性質を備えており、システム変動分析を適用することで、その性質がかなり雲に近いものであったとしても、効果的な予測が可能になると期待される。
 では、国内紛争がBlack Swanとしての性質を持つものである場合はどうか。ここで、もしBlack Swanと呼ばれる事象が存在した場合、それはBlack Swanの定義上、予測をすることは絶対に不可能である。したがって、タレブがなぜ本質的に予測不可能な事象が存在すると主張したのかについて分析する必要があるが、その理論的支柱となるのは、統計学における反復期待値の強法則・弱法則である。これらはそれぞれ、『将来のある時点で何かを期待すると今期待するなら、その何かを今すでに期待していることになる』、『予測ができるぐらい将来を理解するためには、その将来自体から来た要素を取り込まないといけない。将来どんな発見をすることになるかわかっているなら、もう発見したも同然』とする法則である。すなわち、歴史的事件を予測するには技術進歩を予測する必要があるが、技術進歩は本質的に予測できないと主張している(タレブ 2009 : 下巻14-18)。しかし、システム変動分析においては、この「技術進歩」は外圧に相当するものである。安定状態にある国内政治システムに技術進歩という外圧(例えば、新しいコミュニケーション技術の発明)が加わることで、転換点に近づいていたシステムは変動(宗教的活動が活発化)し、異なる安定状態(国内紛争状態)に至る。変動に至る前の外圧に対して脆弱な状態を検出するのがシステム変動分析であり、したがって、こうした技術進歩はシステム変動分析が予測の対象としているものではない。また、反復期待値の法則により技術進歩の予測には過去のデータが参考にならないが、システムの状態は国民の生活水準を表す一般的な変数により評価され、これらの変数の重要度は比較的長い期間変化しないため、過去のデータを活用して予測を立てやすいと考えられる。以上より、前国内紛争状態の予測へと研究の焦点を移すことで、従来予測が困難・不可能とされてきた性質のものに対しても、効果的な予測を行うことができるのである。
では、国内紛争がBlack Swanとしての性質を持つものである場合はどうか。ここで、もしBlack Swanと呼ばれる事象が存在した場合、それはBlack Swanの定義上、予測をすることは絶対に不可能である。したがって、タレブがなぜ本質的に予測不可能な事象が存在すると主張したのかについて分析する必要があるが、その理論的支柱となるのは、統計学における反復期待値の強法則・弱法則である。これらはそれぞれ、『将来のある時点で何かを期待すると今期待するなら、その何かを今すでに期待していることになる』、『予測ができるぐらい将来を理解するためには、その将来自体から来た要素を取り込まないといけない。将来どんな発見をすることになるかわかっているなら、もう発見したも同然』とする法則である。すなわち、歴史的事件を予測するには技術進歩を予測する必要があるが、技術進歩は本質的に予測できないと主張している(タレブ 2009 : 下巻14-18)。しかし、システム変動分析においては、この「技術進歩」は外圧に相当するものである。安定状態にある国内政治システムに技術進歩という外圧(例えば、新しいコミュニケーション技術の発明)が加わることで、転換点に近づいていたシステムは変動(宗教的活動が活発化)し、異なる安定状態(国内紛争状態)に至る。変動に至る前の外圧に対して脆弱な状態を検出するのがシステム変動分析であり、したがって、こうした技術進歩はシステム変動分析が予測の対象としているものではない。また、反復期待値の法則により技術進歩の予測には過去のデータが参考にならないが、システムの状態は国民の生活水準を表す一般的な変数により評価され、これらの変数の重要度は比較的長い期間変化しないため、過去のデータを活用して予測を立てやすいと考えられる。以上より、前国内紛争状態の予測へと研究の焦点を移すことで、従来予測が困難・不可能とされてきた性質のものに対しても、効果的な予測を行うことができるのである。
予測に対する人為的な介入と、前紛争状態分析による対策
 しかし、この手法を用いて予測を行ったところで、人為的な介入によりそれを無効にすることは依然として可能である。これは予測という行為が持つ普遍的な性質として克服不可能なものであるが、ここで紛争予測の研究が目指すべき目標について検討することで、前国内紛争状態の予測は、この問題点によっては意義を損なわれないことがわかるだろう。従来の「国内紛争勃発の予測」は予測が外れた場合(例えば、起こると予測された国内紛争が生じなかった場合)、その予測モデルは性能が低いと判断される。すなわち、自身が作成したモデルの性能を高く評価されたいと思う研究者は、モデルの予測通りに国内紛争が生じることを願うことになるが、これは平和構築の観点とは相反する態度である。本来の紛争予測の目的は、起こりうる紛争を予測し、それを回避できるような政策を構築して平和を維持することであり、予測を的中させること自体が重要なのではない。しかし、紛争のあり・なしの二分法を用いる予測手法においては、他のモデルとの性能比較のために、あたかも予測を的中させることが至高の目標であると錯覚させられることがある。これに対し、「前国内紛争状態の予測」においては、得られた予測を積極的に公開し、国内紛争勃発リスクの高い地域に対して、紛争を回避するよう働きかけることができる。その際、国内政治システムのどの側面が転換点としての予兆を示しているかについて提示することは、政策的介入の有効性を高めることに繋がる。このような試みとして、既にGlobal Conflict Risk Index(GCRI)(Halkia et al. 2017)などが存在しているが、ここで用いられている手法は従来の「国内紛争勃発の予測」、または説明研究のモデルであり、その精度には疑問が残る。よって、前国内紛争状態の予測を主軸とした新しいRisk Indexを構築することが求められるのである。また、こうして国内紛争が回避された場合も前国内紛争状態が存在した事実は変わらないため、その時の前国内紛争状態の程度を事後的に評価し、モデルの予測値と照合することで、その予測精度を求めることができる。よって、予測が持つモデル比較の明確さという利点を保持しつつ、平和政策構築のための実用性も高めることができるのである。
しかし、この手法を用いて予測を行ったところで、人為的な介入によりそれを無効にすることは依然として可能である。これは予測という行為が持つ普遍的な性質として克服不可能なものであるが、ここで紛争予測の研究が目指すべき目標について検討することで、前国内紛争状態の予測は、この問題点によっては意義を損なわれないことがわかるだろう。従来の「国内紛争勃発の予測」は予測が外れた場合(例えば、起こると予測された国内紛争が生じなかった場合)、その予測モデルは性能が低いと判断される。すなわち、自身が作成したモデルの性能を高く評価されたいと思う研究者は、モデルの予測通りに国内紛争が生じることを願うことになるが、これは平和構築の観点とは相反する態度である。本来の紛争予測の目的は、起こりうる紛争を予測し、それを回避できるような政策を構築して平和を維持することであり、予測を的中させること自体が重要なのではない。しかし、紛争のあり・なしの二分法を用いる予測手法においては、他のモデルとの性能比較のために、あたかも予測を的中させることが至高の目標であると錯覚させられることがある。これに対し、「前国内紛争状態の予測」においては、得られた予測を積極的に公開し、国内紛争勃発リスクの高い地域に対して、紛争を回避するよう働きかけることができる。その際、国内政治システムのどの側面が転換点としての予兆を示しているかについて提示することは、政策的介入の有効性を高めることに繋がる。このような試みとして、既にGlobal Conflict Risk Index(GCRI)(Halkia et al. 2017)などが存在しているが、ここで用いられている手法は従来の「国内紛争勃発の予測」、または説明研究のモデルであり、その精度には疑問が残る。よって、前国内紛争状態の予測を主軸とした新しいRisk Indexを構築することが求められるのである。また、こうして国内紛争が回避された場合も前国内紛争状態が存在した事実は変わらないため、その時の前国内紛争状態の程度を事後的に評価し、モデルの予測値と照合することで、その予測精度を求めることができる。よって、予測が持つモデル比較の明確さという利点を保持しつつ、平和政策構築のための実用性も高めることができるのである。
事例分析:ルワンダ虐殺(1994年)

虐殺の傷跡を残すントラマ教会(Ntrama Church)[26]
システムとしての紛争に対する定性的分析
このように、前紛争状態の予測に焦点を設定した研究においては、事件や民族対立のような紛争の最終的な引き金となる要因より、それが重大なものとなり得るシステムの状態の重要性を強調するが、この観点は紛争の定性的分析からも支持される。その例として、紛争の「本質主義」に対する批判がある。紛争の「本質主義」とは、紛争を「民族紛争」、「文明の衝突」、「『文明』対『野蛮』」などの構図として認識し、これらの「民族」「文明」「野蛮」といった不変の「本質」が、不可避的に問題を引き起こしていると考える思考法である。しかし、異なる民族や文化が一つの国家の中で共存してきた事例などを考えると、この思考法では、なぜ特定の時期・地域に限って紛争が生じたのかを説明することができない。したがって、こうした「本質」は歴史的に形成されてきたものであり、その背景には差異の強調を駆り立てるような構造的問題があったと考えるのが妥当であると分析される(遠藤 2006)。結局、とある「原因」が国内紛争の引き金となるか否かは、その影響を受けた国内政治システムの状態に依存すると言える。よって、ルワンダの例では、国内政治システムは1994年の時点で外圧に対して脆弱な転換点を迎えており、そこに印象的な事件が生じることで、民族間の平和を維持することができず、過激な反応が惹起されたと考えることができる。
問題点と対策
 これまで前紛争状態の予測に焦点を当てた研究の利点について述べてきたが、この手法にもいくつか限界がある。第一に、外圧によるノイズが大きい場合、システムは転換点から離れた状態でも変動を生じうる。対策としては、モーメント拡張によりデータの次元を増やしてノイズを縮小する手法が提唱されている(Liu et al. 2015)が、非常に大きな外圧は明確な転換点が無い場合でもシステムの大変動として観察される(Scheffer et. al 2009 : Box1-a参照)ため、事例によっては分析に適さない場合がある。第二に、分析に用いられるデータは年単位のものがほとんどであり、前紛争状態の予測のように期間(ウインドウ)をとって分析を行う場合、予測は大まかなものとなり得る可能性がある。意味のある標準偏差や相関係数を求めるためには少なくとも4~5個のデータが必要となり、したがって、前紛争状態は4~5年間隔での評価となる。そのため、より短い間隔での予測が必要な場合にはIntegrated Crisis Early Warning System(ICEWS)(Boschee et al. 2018)などのデータ間隔の短いデータセットを用いることが考えられる。こうしたデータセットは新聞記事や政治的文書を情報源としたものが多く、自然言語処理の手法により変数を抽出することになる(例えば、Mueller & Rauh 2018)。最後に、紛争・非紛争状態の区別は容易であるが、前紛争・非前紛争状態の区別は困難である。最も簡単な方法としては、紛争勃発前の数年間を一括して前紛争状態と定義することが考えられるが、明確な基準は存在しないため、機械学習を繰り返して適切な範囲を求める必要がある。また、機械学習の結果、偽陽性や偽陰性が出た場合に、それらのデータを定性的に検証して前紛争・非前紛争状態の判断を再度行うことは、国や時代の実情にあった分析を可能にすると考えられる。
これまで前紛争状態の予測に焦点を当てた研究の利点について述べてきたが、この手法にもいくつか限界がある。第一に、外圧によるノイズが大きい場合、システムは転換点から離れた状態でも変動を生じうる。対策としては、モーメント拡張によりデータの次元を増やしてノイズを縮小する手法が提唱されている(Liu et al. 2015)が、非常に大きな外圧は明確な転換点が無い場合でもシステムの大変動として観察される(Scheffer et. al 2009 : Box1-a参照)ため、事例によっては分析に適さない場合がある。第二に、分析に用いられるデータは年単位のものがほとんどであり、前紛争状態の予測のように期間(ウインドウ)をとって分析を行う場合、予測は大まかなものとなり得る可能性がある。意味のある標準偏差や相関係数を求めるためには少なくとも4~5個のデータが必要となり、したがって、前紛争状態は4~5年間隔での評価となる。そのため、より短い間隔での予測が必要な場合にはIntegrated Crisis Early Warning System(ICEWS)(Boschee et al. 2018)などのデータ間隔の短いデータセットを用いることが考えられる。こうしたデータセットは新聞記事や政治的文書を情報源としたものが多く、自然言語処理の手法により変数を抽出することになる(例えば、Mueller & Rauh 2018)。最後に、紛争・非紛争状態の区別は容易であるが、前紛争・非前紛争状態の区別は困難である。最も簡単な方法としては、紛争勃発前の数年間を一括して前紛争状態と定義することが考えられるが、明確な基準は存在しないため、機械学習を繰り返して適切な範囲を求める必要がある。また、機械学習の結果、偽陽性や偽陰性が出た場合に、それらのデータを定性的に検証して前紛争・非前紛争状態の判断を再度行うことは、国や時代の実情にあった分析を可能にすると考えられる。
おわりに
本論文では紛争予測の研究が持つ利点を説明するとともに、その根本的な限界を克服するため、システム変動の予兆に着目した手法を導入し、研究の焦点を従来の「紛争勃発の予測」から、「前紛争状態の予測」へと移すことを提唱した。この手法により、これまで予測が困難と考えられてきた、複雑な構造を持つシステムに対しての予測が可能となった。また、予測された前紛争状態を積極的に公表することで政策構築上の実用性を向上させることができるが、この時、紛争予測の研究が持つ比較の明確さという利点は損なわれないことについても示した。前紛争状態の予測にはまだいくつかの問題点は存在するが、それらすべてに共通する対策は、歴史的な事例を定性的に吟味することである。定性的な分析はシステム変動分析など計量分析の方針を明確化し、より解釈性の高いモデルをもたらすと考えられる。
複雑性が高まっていく世界において、今後もより実用性に優れた研究が求められるであろう。そうした中で、平和・紛争分析が説明能力よりも予測能力の高いモデルを重視するようになったことは歓迎されるべきである。予測研究が今後もより広い支持を受けていくためには、様々な側面から指摘される根本的な限界を克服していく必要があるが、「前紛争状態の予測」はその解の1つとなることが期待される。
参考文献
- 遠藤誠治(2006)「現代紛争の構造とグローバリゼーション」大芝亮・藤原帰一・山田哲也編『平和政策』31-53頁, 有斐閣.
- 大西義久(2016)「<増補2>「現場の人」の開発援助哲学―その後のルワンダ・アフリカ経済と東アジア経済の比較をふまえて」服部正也著『ルワンダ中央銀行総裁日記』増補版7版, 323-337頁, 中公新書.
- タレブ, ナシーム ニコラス [望月衛訳](2009)『ブラック・スワン―不確実性とリスクの本質』上・下巻, ダイヤモンド社.
- ナイ, ジョセフ , ジュニア・デイヴィッド A. ウェルチ [田中明彦・村田晃嗣訳]『国際紛争―理論と歴史』(2017)原書第10版, 有斐閣.
- 中川拓麻・奥牧人・合原一幸(2016)「動的ネットワークマーカーによるシステムの転移の予兆検出」『生産研究』68巻3号, 271-274頁.
- 服部正也(2016)「<増補1>ルワンダ動乱は正しく伝えられているか」服部正也著『ルワンダ中央銀行総裁日記』増補版7版, 299-322頁, 中公新書.
- ポパー, カール [森博訳](1974)『客観的知識―進化論的アプローチ』木鐸社.
- Blei, David M. 2014. “Build, compute, critique, repeat: Data analysis with latent variable models,” Annual Review of Statistics and Its Application, 1(1): 203-232.
- Boschee, Elizabeth, Jennifer Lautenschlager, Sean O’Brien, Steve Shellman, James Starz, and Michael Ward. 2018. ICEWS Coded Event Data, Harvard Dataverse. doi: 10.7910/DVN/28075.
- Chadefaux, Thomas. 2017. “Conflict forecasting and its limits,” Data Science, 1: 7-17.
- Chen, Luonan, Rui Liu, Zhi-Ping Liu, Meiyi Li, and Kazuyuki Aihara. 2012. “Detecting early-warning signals for sudden deterioration of complex diseases by dynamical network biomarkers,” Scientific Reports, 2: 342.
- Colaresi, Michael and Zuhaib Mahmood. 2017. “Do the robot: Lessons from machine learning to improve conflict forecasting,” Journal of Peace Research, 54(2): 193-214.
- Collier, Paul, and Anke Hoeffler. 2004. “Greed and grievance in civil war,” Oxford Economic Papers, 56: 563-595.
- Dupuy, Kendra, Scott Gates, Håvard Mokleiv Nygård, Ida Rudolfsen, Siri Aas Rustad Håvard Strand, and Henrik Urdal. 2017. “Trends in Armed Conflict, 1946–2016,” (Oslo: Peace Research Institute Oslo), <https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1373&type=publicationfile>, accessed 29 May 2018.
- Fariss, Christpher J. 2014. “Respect for human rights has improved over time: modeling the changing standard of accountability,” American Political Science Review, 108(2): 297-318.
- Fearon, James D, and David D Laitin. 2003. “Ethnicity, insurgency, and civil war,” American Political Science Review, 97(1): 75-90.
- Greenhill, Brian, Michael D Ward, and Audrey Sacks. 2011. “The separation plot: A new visual method for evaluating the fit of binary models,” American Journal of Political Science, 55(4): 990-1002.
- Halkia, Stamatia, Stefano Ferri, Ines Joubeat-Boitat, Francesca Saporiti, and Mayeul Kauffmann. 2017. The global conflict risk index (GCRI) Regression model: data ingestion, processing, and output methods. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Hegre, Håvard, Nils W Metternich, Håvard Mokleiv Nygård, and Julian Wucherpfennig. 2017. “Introduction: Forecasting in peace research,” Journal of Peace Research, 54(2): 113-124.
- Liu, Rui, Pei Chen, Kazuyuki Aihara, and Luonan Chen. 2015. “Identifying early-warning signals of critical transitions with strong noise by dynamical network markers,” Scientific Reports, 5: 17501.
- Muchlinski, David, David Siroky, Jingrui He, and Matthew Kocher. 2016. “Comparing random forest with logistic regression for predicting class-imbalanced civil war onset data,” Political Analysis, 24(1): 87-103.
- Mueller, Hannes, and Christopher Rauh. 2018. “Reading between the lines: Prediction of political violence using newspaper text,” American Political Science Review, 112(2): 358-375.
- Scheffer, Marten, Jordi Bascompte, William A. Brock, Victor Brovkin, Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos, Hermann Held, Egbert H. van Nes, Max Rietkerk, and George Sugihara. 2009. “Early-warning signals for critical transitions,” Nature, 461(3): 53-59.
- Uppsala University. “Definitions - Department of Peace and Conflict Research - Uppsala University - Sweden,” < http://pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/>, accessed 29 May 2018.
- Ward, Michael D, Brian D Greenhill, and Kristin M Bakke. 2010. “The perils of policy by p-value: Predicting civil conflicts,” Journal of Peace Research, 47(4): 363-375.
- Scott Chacon from Dublin, CA, USA. Ntrama Church Altar.jpg. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ntrama_Church_Altar.jpg


Comments