2階同次線形微分方程式を解く際や、2階非同次線形微分方程式の余関数を求める際には、方程式の係数から特性方程式を作る。
この特性方程式がなぜ重要になるのか、また、その解の性質からなぜ微分方程式の解の形が変わってくるのかについて、式を操作しながら確かめてみる。
ここでは、厳密な証明を行うのではなく、「特性方程式を使うと確かに上手くいくし、この関数が解になるためにはこんな条件が必要になるよね」という感覚を味わってもらうことを目標とする。
特性方程式を用いた定数係数2階同次微分方程式の解法
特性方程式の解の個数(判別式)の条件と、一般解の関係は

を参照。
定数係数2階同次微分方程式の特徴
$$y''+py'+qy=0\tag{1}$$
今回のテーマとなる(定数係数)2階同次微分方程式は、上記のように書ける。
すなわち、ある関数とその1階微分、2階微分を適当な係数 \(p,q\) のもとに足し合わせると0になるという方程式である。
このような関係が成り立つためには、 \(y\) は微分しても項の形が変化しない関数である必要がある。
なぜならば、微分によりとある項が消えたり、新しい項が増えたりした場合、 \(y, y', y''\) の加減算によってそれらを消すことが不可能になるためである。
(例) \(y=2x^2+3x+1\) のとき
$$y'=4x+3$$
$$y''=4$$
より、 \(x^2\) の項は \(y\) にしか存在しておらず、 \(y', y''\) にどのような係数を掛けて足し合わせたとしても消去できない。
指数関数の性質
「微分しても項の形が変化しない」という性質をみたす代表的な関数として、指数関数が挙げられる。
実数 \(\lambda\) を用いて
$$y=e^{\lambda x}\tag{2}$$
という関数を考えると
$$\frac{dy}{dx}=\lambda e^{\lambda x}$$
より、微分しても係数を変化させるだけで、項の形に影響を与えない。
よって、この関数が微分方程式の解の第一候補であると考えることができる。
指数関数が微分方程式の解となる条件
では、 \((2)\) が解となるためには、 \(\lambda\) にどのような条件があるのだろうか。
実際にこの関数を微分し、 \((1)\) に代入して検証してみる。
$$y'=\lambda e^{\lambda x}$$
$$y''=\lambda^2 e^{\lambda x}$$
より、 \((2)\) 式に代入して
$$\lambda^2 e^{\lambda x}+p\lambda e^{\lambda x}+qe^{\lambda x}=0$$
$$e^{\lambda x}(\lambda^2+p\lambda+q)=0$$
という方程式が得られるが、 \(e^{\lambda x}>0\) であるため
$$\lambda^2+p\lambda+q=0\tag{3}$$
となり、ここで特性方程式と同じ形の式が登場する。
また以上の計算より、 \(\lambda\) が \((3)\) をみたす実数であるとき、指数関数 \((2)\) が微分方程式 \((1)\) の解となることがわかる。
指数関数から一般解を考える
これまでの計算では、微分方程式 \((1)\) の解の1つを求めたに過ぎない。
微分方程式を解くという行為は、その方程式となりうるすべての関数を任意定数を用いて一般的な形で表現する(一般解を求める)ことを指す。
よって、この単純な指数関数を拡張し、より複雑な解の候補を探索する必要がある。
最も単純な拡張として、任意の係数を掛けることが考えられる。
すなわち、 \((2)\) より一般に
$$y=Ce^{\lambda x}\tag{4}$$
は微分方程式 \((1)\) の解となる。
そして結論から述べると、以下の形で書ける関数が微分方程式 \((1)\) の解の候補となる。
- \(y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}\)
- \(y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_0 x}\)
- \(y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)\)
( \(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \alpha, \beta\) は実数、 \(C_1, C_2\) は任意定数)
以下、それぞれが指数関数 \((2)\) または \((4)\) から拡張される理由と、それぞれが解となる条件について解説する。
\(y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}\)
微分は項ごとに行われるため、指数関数同士を足し合わせても「微分しても項の形が変化しない」という性質に影響を与えない。
ただし、足し合わせることができる数には上限がある。
なぜならば、指数関数 \((2)\) または \((4)\) が微分方程式 \((1)\) の解となるためには、 \(\lambda\) が \((3)\) の条件をみたす必要があり、これが2次方程式であることより実数解は最大で2種類であるためである。
よって特性方程式 \(\lambda^2+p\lambda+q=0\) について判別式 \(D>0\) であり、2個の実数解を \(\lambda=\lambda_1, \lambda_2\) とすると、微分方程式 \((1)\) の一般解は
$$y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}$$
と書ける。
異なる見方をすると、特性方程式の実数解が \(\lambda=\lambda_1, \lambda_2\) の2つある場合は \(y=e^{\lambda_1 x}\) も \(y=e^{\lambda_2 x}\) も解となるが、これらを同時に表現するために
$$y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}$$
と書いている( \(C_1=1, C_2=0\) で \(y=e^{\lambda_1 x}\) 、 \(C_1=0, C_2=1\) で \(y=e^{\lambda_2 x}\) が表現できる)。
\(y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_0 x}\)
積の微分法則
$$\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$
より、指数関数との積になっている場合は、 \(n\) 次多項式を微分しても項が失われない。
ただし、2階線形微分方程式の解の場合は、 \(n=1\) に限られる。
(以降の計算を \(n\geq 2\) でやってみるとうまくいかないことがわかる)
$$y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_0 x}$$
を微分して微分方程式 \((1)\) に代入すると
$$y'=C_2e^{\lambda_0 x}+(C_1+C_2x)\lambda_0e^{\lambda_0 x}$$
$$=\{C_2+(C_1+C_2x)\lambda_0\}e^{\lambda_0 x}$$
$$y''=C_2\lambda_0e^{\lambda_0 x}+C_2\lambda_0e^{\lambda_0 x}+(C_1+C_2x)\lambda_0^2e^{\lambda_0 x}$$
$$=\{2C_2\lambda_0+(C_1+C_2x)\lambda_0^2\}e^{\lambda_0 x}$$
より
$$y''+py'+qy$$
$$=[2C_2\lambda_0+(C_1+C_2x)\lambda_0^2+p\{C_2+(C_1+C_2x)\lambda_0\}+q(C_1+C_2x)]e^{\lambda_0 x}$$
$$=\{C_1(\lambda_0^2+p\lambda_0+q)+C_2(2\lambda_0+p)+C_2(\lambda_0^2+p\lambda_0+q)x\}e^{\lambda_0 x}=0\tag{5}$$
ここで、 \(\lambda_0\) は \(\lambda_0^2+p\lambda_0+q=0\) をみたす実数であるため、 \((5)\) 式は
$$C_2(2\lambda_0+p)e^{\lambda_0 x}=0$$
となり、 \(C_2\neq0\) とすると
$$2\lambda_0+p=0\Leftrightarrow\lambda_0=-\frac{p}{2}$$
として、 \(\lambda_0\) は1つに絞られる。
よって特性方程式 \(\lambda^2+p\lambda+q=0\) について判別式 \(D=0\) であり、重解を \(\lambda=\lambda_0\) とすると、微分方程式 \((1)\) の一般解は
$$y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_0 x}$$
と書ける。
なお、このとき特性方程式は
$$\left(\lambda+\frac{p}{2}\right)^2=0$$
と変形でき、その重解は \(-\frac{p}{2}\) である。
\(y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)\)
最後に、指数関数以外で「微分しても項の形が変化しない」という性質を持つ関数を考える。
三角関数 \(\cos\beta x,\sin\beta x\) は微分によりお互いの形を往復することになるため、これらの和である
$$C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\tag{6}$$
は微分しても項の形が変化しない。
これと指数関数を掛けた
$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)\tag{7}$$
を微分方程式 \((1)\) の一般解の候補とする。
なお、 \((7)\) は \(\alpha=0\) とすることで \((6)\) に等しくなる。
$$E_1=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$$
$$E_2=e^{\alpha x}(C_2\cos\beta x-C_1\sin\beta x)$$
とおくと
$$y=E_1$$
$$y'=\alpha E_1+\beta E_2$$
$$y''=\alpha(\alpha E_1+\beta E_2)+\beta(\alpha E_2-\beta E_1)$$
$$=(\alpha^2-\beta^2)E_1+2\alpha\beta E_2$$
よって、微分方程式 \((1)\) に代入して
$$y''+py'+qy=(\alpha^2-\beta^2)E_1+\alpha\beta E_2+p(\alpha E_1+\beta E_2)+qE_1$$
$$=(\alpha^2+p\alpha+q-\beta^2)E_1+(2\alpha+p)\beta E_2=0$$
が得られる。
ここで \(\beta=0\) のとき、 \(\alpha^2+p\alpha+q=0\) ならば方程式をみたすが、このとき
$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos 0+C_2\sin 0)=C_1e^{\alpha x}$$
となり、三角関数の項が消えてしまう。
よって \(\beta\neq 0\) とすると
$$\begin{eqnarray}\left\{\begin{array}{l}\alpha^2+p\alpha+q-\beta^2 = 0 \\ 2\alpha+p = 0 \end{array}\right.\end{eqnarray}$$
より、下段より
$$\alpha=-\frac{p}{2}$$
上段に代入して
$$\frac{p^2}{4}-\frac{p^2}{2}+q-\beta^2=0$$
$$\beta^2=q-\frac{p^2}{4}=\frac{4q-p^2}{4}$$
$$\beta=\frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}$$
となる。
ところで、特性方程式 \(\lambda^2+p\lambda+q=0\) を解の公式を用いて解くと
$$\lambda=\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}=-\frac{p}{2}\pm\frac{\sqrt{p^2-4q}}{2}$$
であり、これが虚数解となる場合は
$$\lambda=-\frac{p}{2}\pm\frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}i=\alpha\pm\beta i$$
と対応する。
よって特性方程式 \(\lambda^2+p\lambda+q=0\) について判別式 \(D=p^2-4q< 0\) であり、虚数解を \(\lambda=\alpha\pm\beta i\) とすると、微分方程式 \((1)\) の一般解は
$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$$
と書ける。

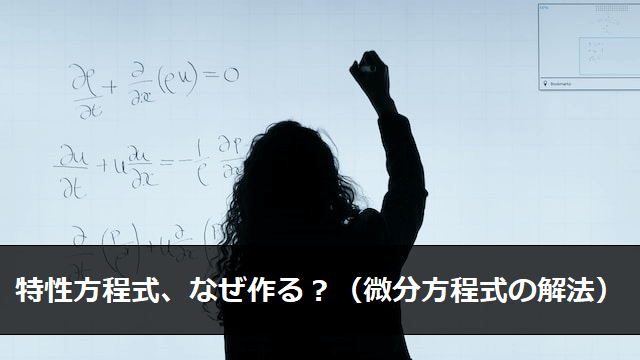
Comments