はじめに半導体の性質を把握し、それにもとづいてパーツを作り、最終的にコンピュータが動く原理を理解します。
このシリーズの記事を読むことで、コンピュータの原理をその構成要素にもとづき、0から深く理解することができます。
全体の流れ
現代社会を支えるコンピュータの進化は急速であり、その構造はもはやブラックボックスです。
しかし、「計算機」としてのコンピュータの本質は、その誕生から現在まで変わりません。
本シリーズでは、この計算を行う電子機器がどのように作られるかを素材のレベルから解説します。
鍵となる素材は「半導体」で、これを加工・接合することによって「ダイオード」や「トランジスタ」と呼ばれるパーツを作ることができます。
このうち、トランジスタ(特に「MOSFET」と呼ばれる種類)はスイッチ機能を有する重要なパーツで、これを複数組み合わせることによって、「NOTゲート」・「ORゲート」・「ANDゲート」という論理を制御できる回路を組むことができます。
さらにこれらのゲートを組み合わせることで「半加算器(1bit加算器)」という1桁の足し算を行う回路を作ることができ、これを任意の桁に拡張した「全加算器(n bit加算器)」こそ、コンピュータの本質ともいえる回路です。
このように、「下位のパーツを組み合わせて、より高度なパーツを構成する」という工程を繰り返してコンピュータは作られています。
昨今では、人工知能といった、人間を凌駕する機能をもつコンピュータですが、これを素材の段階から1つ1つ組み立てていく感覚を体験してもらえたら幸いです。
記事一覧
n型半導体/p型半導体―作り方と動作原理
「n型半導体・p型半導体とは何か?」 その作り方と動作原理を解説します。
この記事を読むことで、コンピュータを構成する素材の性質や、それがなぜ電気を流すことができるのかを理解することができます。
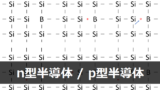
ダイオードの原理と整流作用
「ダイオードとは何か?」 その作り方と動作原理を解説します。
この記事を読むことで、なぜダイオードが電気を一方向にだけ流すことができるのか、を理解することができます。
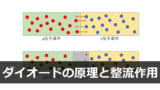
トランジスタの原理
「トランジスタとは何か?」 その作り方と動作原理を解説します。
この記事を読むことで、なぜトランジスタがスイッチや増幅器として働くのか、NPN型・PNP型とは何か、を理解することができます。
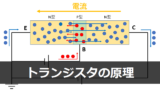
MOSFETの原理と種類―NMOSとPMOS
「MOSFETとは何か?」 その作り方と動作原理を解説します。
この記事を読むことで、MOSFETが電圧制御のスイッチとして働く理由や、NMOS/PMOSの違いを理解できます。

CMOSとは?NOTゲートの動作原理をもとに解説
「CMOS(相補的MOS)とは何か?」
構成要素であるNMOS/PMOSを紹介した上で、代表的な論理回路であるNOTゲートを例に解説します。
この記事を読むことで、NMOS/PMOSを組み合わせて論理回路を作る方法や、その動作の分析の仕方がわかるようになります。
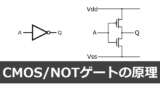
ORゲートの回路図と動作原理
トランジスタを使ってORゲートを作る方法について解説します。
この記事を読むことで、ORゲートが「AまたはB」を電気回路で表現できる理由がわかります。
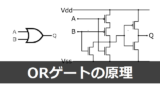
ANDゲートの回路図と動作原理
トランジスタを使ってANDゲートを作る方法について解説します。
この記事を読むことで、ANDゲートが「AかつB」を電気回路で表現できる理由がわかります。
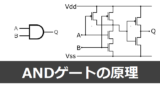
半加算器(1bit加算器)の回路図と動作原理
「半加算器とは何か?」
半加算器を構成する回路図を読み解いて、その動作原理を解説します。
この記事を読むことで、NOT/OR/ANDの論理回路を組み合わせて足し算を行う基本的な方法について理解できます。
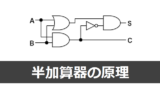
全加算器(n bit加算器)の回路図と動作原理
「全加算器とは何か?」
全加算器を構成する回路図を読み解いて、その動作原理を解説します。
この記事を読むことで、半加算器の桁上げ処理を連結し、任意の桁の足し算を行う回路を作る方法が理解できます。
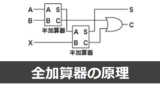
【補講】トランジスタの増幅機能
現在執筆中です。

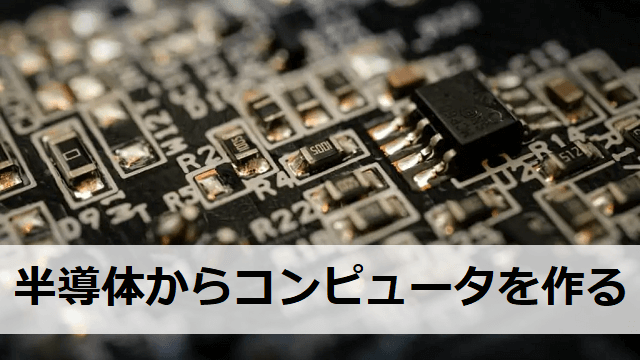
Comments